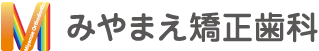矯正について
こどもの矯正
小児の矯正治療は歯の生え変わりの管理も含めて重要です。
当院では、小児歯科医と連携して治療すべき歯の早期発見と予防に努め、成長に合わせた歯と顎のバランスをコントロールし、出っ歯や受け口になることを防ぐことが可能です。
詳しくはこちら大人の矯正
「矯正をするのはもう遅い」と思っていませんか?まずは、ご相談下さい。
成人し、歯の成長が終わってからでも矯正治療が可能です。歯と歯肉が健康な状態であれば、大人の矯正は年齢に関係なく始めることができます。
詳しくはこちら目立ちにくい矯正治療
個々の患者様に最適な、オーダーメイドの矯正装置を製作いたします。
大人、特に社会人の方は、お仕事の関係上、目立たない矯正治療(裏側矯正)を選ぶ方が増えてきております。
矯正装置を歯の裏側に付ければ、人に気付かれることなく矯正治療を行うことができます。